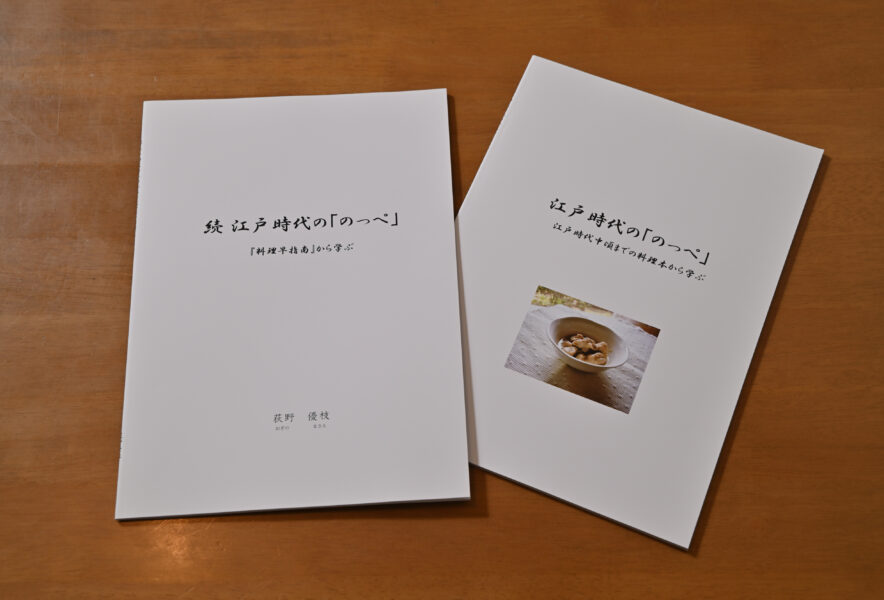「のっぺ」のルーツと思われる料理は、中国式精進料理である普茶(ふちゃ)料理。1250年、南宋から渡来し鎌倉建長寺を開山した禅僧の蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)が伝えた禅寺料理の一つで、野菜などを煮込んでクズ粉でとろみをつけた葛寄せ料理でした。
安土桃山時代には、この普茶料理が庶民の料理として受け継がれました。1593年刊行とされる料理本『南方録(なんぽうろく)』には「雲雀(ひばり)のっぺい」が登場し、これが「のっぺ」の最初らしいと言われています。
江戸時代には『料理物語』(寛永20・1643年)の「煮物之部」に、鴨を用いたクズかき小煮物「のつへいとう」と紹介されています。「鴨をいり鳥のごとくつくり、だしたまりにて煮る。煮え立ち候とき、加減吸い合わせうどんの粉をだしにてとき粘るほどさし、煮え立ち候とき出し候。しぎ、うづらなどもよし」。また「ふののつへいとう」の項目では「麩を油にて揚げ大きに切り、鴨の料理の如くいたしてよし」とも記されています。(『江戸時代料理本集成第一巻』参照)
『料理網目調味抄』享保15(1730)年では蒼鷺(あおさぎ)を用いています。当時は鳥肉が必ず入るクズかき料理だったようです。(『日本料理由来事典』参照)
『料理歌仙の組糸(くみいと)』(延享5・1748年)では鳥肉の代用で串海鼠(くしこ・ナマコをゆでて串に刺し干したもの)が使われているところから、煎りナマコや貝類が鳥肉に替わるようにもなってきたと思われます。(『食生活語彙五種便覧』参照)
近代になると、材料が少しずつ変わり、鳥肉の替わりに貝類、魚類などが使われるようになります。そして根菜類も取り合わせるようになり、クズ粉や片栗粉でトロミをつける替わりに、サトイモのぬめりを生かして作られることも多くなりました。
「のっぺ」「のっぺい」「ぬっぺ」「ぬっぺい」など、名称はさまざまですが、現代でも日本全国各地で作られており、それぞれの地域ごとに特色をもつ郷土料理として受け継がれています。
語源
汁がねばってぬらりとしているところから「ぬっぺい」と呼ばれ、それがなまって「のっぺい」「のつへい」となったようです。餅のようにねばるので、漢字のあて字は「濃餅」「能平」「濃平」と書きます。
(『たべもの語源辞典』参照)
取材・文:野崎史子 2024年12月